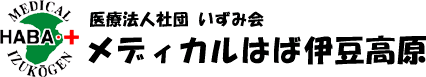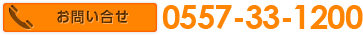腰痛を予防するとは・・・
2025.07.10
こんにちは、当院でリハビリテーションを担当させていただいている理学療法士です。
整形外科疾患で皆様が耳にすることの多い疾患名として、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎分離すべり症、腰椎椎間板ヘルニアなどが挙げられます。それぞれ治療方法が違い、主治医の先生方と時間をかけて話し合われ、リハビリテーションを含めた治療方針を決めていらっしゃることと思われます。一般的に腰痛とは、外科的にも内科的にも全身に及ぶ様々な病態のもと現れる症状を言います。それぞれの専門科で疾患に対する医学的な治療を行ったうえで、回復期・生活期に於ける腰痛症状に対する基本的な捉え方の一例をお話しさせて頂きます。
病気を患い体力が落ちると全身の筋肉量が低下します。それにより姿勢の保持が難しくなり、腰痛などの症状が現れやすいと考えられています。また、腰椎がつぶれたり、椎体と椎体の間が狭くなるなど構造的な問題で、腰痛とともに痺れなどの神経症状を訴える方も多くいらっしゃるようです。
体力の低下や加齢とともに低下しやすい筋肉を主にアウターマッスルといい、身体の表面から触れることのできる大きく強力な筋肉です。これら表層部にある力強い筋肉に頼らず、身体の深部で骨格を動かすことのできるインナーマッスルを上手に使えれば、骨と骨のつなぎ目である関節部を安定させ、少ないエネルギーで身体全体を滑らかに動かすことが可能になっていきます。
私たちの多く(特に 10代~20代の若者世代や体力に自信がある方など)は、通常アウターマッスルに頼って日常生活を過ごしがちです。インナーマッスルを意識しないで日常を送っていると、インナーマッスルには血流が流れにくくなり、それ自体が固く柔軟性をなくし、関節や椎体同士の動きがギコチナクなっていき、アウターマッスルに過度な緊張状態を強いるようになります。腰痛を訴えやすい体幹部でいうと、腰椎の近位部にある腹横筋などのインナーマッスルを働かせる習慣が身に付けば、腰椎同士の動揺を安定化させ、体幹部は固定としての働きや、脊柱の柔軟性を引き出す働きなど、体幹を中心に滑らかな全身の動きを得られるようになります。また、動作に先立った腹横筋インナーマッスルの収縮を先に得るということは、重いものを持ち上げたり、ダイナミックな動きを伴う動作時に必要な身体のエネルギー量と運動方向を事前に予測して、安定した滑らかな動作につなげるという、フィードフォワード制御理論に基づいた考え方でもあります。
体幹部のインナーマッスルトレーニング方法を具体的に記します。
仰向けに寝て両ひざを立て、両手をへその下(下腹部)に置き、リラックスした状態で行います。へその下に腹横筋というインナーマッスルがあります。へその下を意識的に凹まし続けることで腹横筋が働くようになります。深部の筋肉が働いているときはへその下を触っても表面の筋肉は固くならず、アウターマッスルとしての表層面は柔らかい状態を保ちます。また、腹横筋が収縮することで骨盤が後方へ少し傾斜します。それと同時に腰椎背部と床面との隙間を埋めるように床面に向かって背中を押します。へその下を凹ませるのと腰背部で床面を押す動作を同時に行いながら、呼吸は息を吐くようにします。呼気を吐ききったら、意識している筋肉も緩め一旦リセットして1回分です。呼吸のリズムと動作を合わせるよう試みてください。酸素を吸いこみ、再び息を吐きながら先程と同じように腹横筋を収縮させ、腰背部を床面に押す動作を何度か繰り返してください。徐々に下腹部周辺が温かく感じるようになります。呼気(息を吐く)時間は人によりますが 5秒~10秒程度が適当だと思います。動作中は呼吸を止めず、全身をリラックスさせながら行うことが大切です。リラックスした仰向けの姿勢で腹横筋の収縮と呼吸のタイミングを身につけたら、座位や立位でも同様に行うことで、より現実に即したインナーマッスルの収縮を身につけられると思います。日中の生活時間内で運動するタイミングとしては、実際に活動をする前に 5回~10回程度行うことで、無理のない滑らかな動きができるようになってくるでしょう。
世代を問わず、多くの皆様が悩まれている症状の一つである腰痛。年齢や性別、体格や体力の違いに対して、無理のない身のこなしを再獲得するため、インナーマッスルの重要性を再認識していただければと思います。疾患や症状に対して医療的な処置を行った後、腰痛症状緩和のため身体の動かし方を見直していただく方法を述べてきました。腰痛対策は決して一つではありません。皆様の信頼される主治医の先生や療法士の先生方と話し合いを重ねながら、また地道に運動療法を継続するための環境を生活の一部に取り込みながら、腰痛の緩解を目指してお過ごしください。
文責 吉和田 裕資